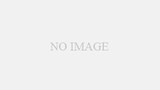Mr.Children「Another Mind」の解説と歌詞考察だよ♪
もうひとりの自分
楽曲紹介
楽曲収録CD
| 概要 | 収録作品 | 発売日 |
|---|---|---|
| 3rd ALBUM | Versus | 1993年9月1日 |
| 特典CD(ライブVer.) | Split the Difference | 2010年11月10日 |
作詞:桜井和寿/作曲:桜井和寿・小林武史/編曲:小林武史&Mr.Children(管編曲: 山本拓夫)
アルバム『Versus』累計売上:80.2万枚
豆知識
アルバムジャケット情報
- 撮影場所:沖縄(コンセプトは特にない)
- アートディレクター:信藤三雄率いるContemporary Production
- 撮影:藤代冥砂
MV(ミュージックビデオ)情報
なし
ミュージックビデオはございません
タイトルについて

社会に合わせて振る舞う“作られた自分”。
また、人に愛されるため、期待に応えるために生まれた“仮面”。
それが「Another Mind」。
歌詞考察
1番 Aメロ(何故に卑屈な〜)
何故に卑屈な微笑浮ぶ この街角
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
行き交う人の波が
奏でてる不協和音
「卑屈な微笑」とは、謙遜し、本心を隠しながら浮かべてしまう、作り笑いのようなものです。
街角という日常の一場面で、行き交う人々は誰にも本音を見せられないまま、無意識に自分を守ろうとしている。
そこには個性を失ったような、心の通い合っていない無機質な空気感が感じられます。
「不協和音」は、すれ違う人々の心がバラバラで、互いに響き合っていないことを意味しているのでしょう。
皆それぞれ自分の思いを抱えて生きているけれど、それが共鳴することはなく、むしろ雑音のように響き合っている。
そして表向きは平然を装っていても、心の奥では孤独や違和感を抱えながら生きている。
そうした社会の息苦しさが描かれています。
1番 Bメロ(自分を〜)
自分を打ち砕くリアルなものは
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
偽りだと目を伏せてた孤独な Teenage
「自分を打ち砕くリアルなもの」というのは、社会から突きつけられる評価・期待・挫折といった、胸が痛むような“現実”のこと。
人は学校、家庭、社会の中で、自分の理想とは違う現実に何度も直面し、そのたびに心が折れそうになります。
でも、まだ若かった頃の主人公は、それを正面から受け止めきれずに、「偽りだ」と自分に言い聞かせ、あえて目をそらしていた。
多感な思春期、他人とうまくつながれず、主人公はひとり思い悩んでいたのかもしれません。
1番 Aメロ2 Bメロ2(幼き日々の〜)
幼き日々のように
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
無邪気なふりをしては
愛すべき人達の 支えの中に溺れてゆく
傷つけずにいられない程
もう子供じゃないのに、あえて無邪気に装ってしまう。
きっとそれは、周囲を安心させたり、自分の弱さを隠したりするための手段として使われているのでしょう。
その無邪気という名の仮面を被りつつ、「愛すべき人達の支えの中に溺れてゆく」。
支えてくれる人がいることは救いでもあります。
でも支えに依存してしまっている自分、甘えてしまっている自分への自覚と、どこかでそれに対する自己嫌悪のような感情もにじんでいます。
「傷つけずにいられない程」というフレーズはそれによって自分が誰かを傷つけ、誰かの重荷になってしまっているという罪悪感。
つまりこのセクションは、「強くなりきれず、無邪気を装って人の優しさにすがりながらも、そのことで大切な人を無意識に傷つけてしまう自分」、そんな心の矛盾と苦しさを吐き出している場面だといえるでしょう。
1番 サビ(誰かが〜)
誰かが定めた自分を演じてる Another Mind
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
流されるのも慣らされてたどり着けばいつも Oh No
社会や他人が期待する“こうあるべき自分”を無意識のうちに演じてしまっている状態。
親・先生・上司・友人、本当の自分はこうじゃないのにと思いながら、僕は皆に対し仮面を被って生きている。
そして、その“演じている”部分こそが「Another Mind」。
これは自分の中にありながら、自分ではない。
本音ではないのに、ずっとそれを装って生きてきた。
その矛盾が、主人公を苦しめてきたのです。
また、「流されるのも慣らされて」という表現から、最初は抵抗していたけれど、次第に何も考えずに流れに従ってしまうようになったという、ある種の“諦め”や“麻痺”が感じ取れます。
かつては「これは自分じゃない」と苦しんでいたはずなのに、いつの間にかその違和感にさえ慣れてしまう。
行き着く先はいつも虚しさや後悔。
それを「Oh No」という言葉で吐き出しています。
2番 Aメロ(何もかも〜)
何もかも投げ出せば It’s just darkside of my heart
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
肩の荷もおりそうさ It’s just darkside of my heart
わずかなプライドを守る為に
誰もが必死で暮らしてる
「It’s just darkside of my heart」=「それは僕の心の闇」。
「もう全部投げ出してしまいたい」という衝動は、誰もがふと感じることのある本音です。
全部投げ出せば誰だって楽になる。
ここでは、その感情を「自分の心のダークサイド」と言い表しています。
その”心の闇”を受け入れることで少しは肩の荷が降りる。
だけど、人は誰もが心のどこかに「これだけは譲れない」という想いや、自分なりの価値観を持っている。
そのプライドを守るために、嘘と矛盾を抱えながらも、誰もが必死で暮らしているのです。
2番 Bメロ(砂に書いた〜)
砂に書いたような“理想”の文字は
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
時代の波にさらわれてく
不思議なこの街
少年時代に描いていた「こうなりたい」「こうあるべきだ」といった理想は、現実の中では長くとどまっていられず、あっけなく壊されてしまう。
その理想を壊したのは、誰か一人のせいではなく「時代の波」だと言います。
つまり、社会の空気や価値観、制度、情報の流れといった、大きくて逆らいようのない“流れ”によって、理想は削り取られていったのです。
“理想”を描いては壊し、誰もが本音を隠して笑いながら、どこかで無理をして生きている。
そんな奇妙な矛盾に満ちた「不思議なこの街」。
このフレーズを通して、「Another Mind」が生まれたのはただ自分が弱かったからではなく、理想を保ちきれない社会の構造そのものがそうさせたのだということが、語られているように感じます。
3番 Bメロ(誰も愛さずに〜)
誰も愛さずにいれるものなら
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
罪な恋に惹かれてゆく この心を消してくれ
愛することは本来、素敵な感情のはずなのに、それが「苦しみ」や「傷み」を生んでしまうのなら、「最初から誰も愛せなければよかった」と願ってしまう。
そして“罪な恋”に惹かれていく。
「罪な恋」とは、自分以外の誰かを傷つけてしまう恋。
「好きになってはいけないと分かっているのに、惹かれてしまう」という抗えない感情、“Another Mind”を示しています。
こんな心があるから、自分は苦しむ。ならば、いっそ「消してくれ」と。
これは感情を押し殺して生きる”もう一人の自分”に対して、本心が最後の抵抗を見せている場面とも捉えられます。
ラスサビ 3番Aメロ(誰かが〜)
誰かが定めた自分を演じてる Another Mind
身動きもできない程に 抱えたプレッシャーはシュール
流されるのも慣らされて たどり着けばいつも Oh No振り向けば夕闇が包むこの街角
<出典>Mr.Children/Another Mind 作詞:桜井和寿
“誰か”が決めた理想像や役割に合わせて、”そうあるべき自分”を演じ続けている。
“本当の自分”ではないものが自分の顔をして日々を歩いている。
その痛みと虚しさを、この曲は歌っています。
演劇の舞台に立っている役者のようなプレッシャーを抱え、がんじがらめになっている自分の姿を見た主人公。
そんな感情を押し殺して生きる自分が、あまりにもシュールで、不自然で、滑稽。
何かを選び取ることもなく、ただ周囲に合わせ、社会に適応するために演じてきた。
その結果、たどり着くのはいつも「Oh No」。
「振り向けば夕闇」=1日が終わる時刻。
街の喧騒、葛藤、感情がすべて闇に包まれていく中で、主人公は一人何を思っているのか…。
社会に合わせて振る舞う“作られた自分”。
また、人に愛されるため、期待に応えるために生まれた“仮面”。
それが「Another Mind」。
聴きどころ
メロディー
サビの力強さと、間奏での叫び・嘆きにも聴こえる、桜井さんのアドリブのような歌がクセになるメロディーです。
※ちなみに間奏で歌っているような歌詞のない即興的な歌唱法を「スキャット」と言います。
また特に好きなのが、ラスサビ前の「消してくれ」の「くれ」!
感情が爆発するような歌とメロディーの切なさにグッとくるんですよね。
ラストに向けて一段とドラマチックな展開を見せる、まさに鳥肌ポイント。
アレンジ
ベースの中川さんはアレンジについて、「すごくシンプルな構成で。これといって難しいこともやってないんですけど、勢いとやる気だけで対応できる曲ですね。(笑)3」とコメントされていました。
確かにミスチルにしてはコード進行もシンプルで、大まかにいうと5種類くらいしか使われていません。
でも36小節もある間奏があり、そこではギターとユニゾンしたソロっぽいフレーズもあるので、聴く側としてはすごく楽しめますね。
JENはこのように語っています。
「これはボクらのやる気です。(笑)この曲って最初っからもう入ってって、間奏でバー…ッて気持ちが昇天して引き込まれてって…なんかブラック・ホールに引き込まれていくような感覚あるんです、あの間奏になると。グワー…ッて引き込まれて、だけどなりゆきにまかせて引き込まれちゃうわけじゃないんですよね。自分の力で進んでる、けど引き込まれる力も感じながら自分で飛んでる、みたいな。で、ブワー…ッて行って、グー…ッ”って行ってって、間奏あけてポンッって出ると、まだこう漂ってるような感じでウロウ口してて。飛んでる力強さを感じてるんです、自分で。で、いちばん最後に、ま、個人的に言えばシンバルでずーっとしめるとこあるんですけども、そこで”スパアーン”ってスヌケちゃって、もう…なんだろ?どういう世界なんだろ、だだっ広いんだけど、暗くないけど…深海みたいな、そういう感じなのかな、これ、言葉で言うの難しいかも。(笑)だからそういうブラックホールに引き込まれるような感触とか、それを『Versus』っていうとヘンかもしれないけど、“曲の持ってる力”対“自分”であったりとか感じますよね。4」
JENらしいコメントですが、「ブラックホールに引き込まれるような感触」っていうのはなんか分かる気がしますね(笑)
あと個人的には、冒頭Aメロのアコギの音が完全に「L」側に振られているので、左のイヤホンを外して聴くと桜井さんのほぼアカペラで聴けるので、当時はそれを楽しんでいました(笑)。
著名人の感想
随時更新します
ライブ&テレビ披露
ライブ
- TVK.LIVE(収録ライブ)
- ’93 Versus TOUR
- 石川工業専門学校 (学園祭ライブ)
- ’94 Special Concert
- SOUND PARADISE ’94
- SOUND CONIFER 229
- SOUND BREEZE ’94
- ’94 tour innocent world
- Split the Difference(スタジオライブ)
オススメ映像作品
Split the Difference
『’94 tour innocent world』以来約16年ぶりの演奏でした。
テレビ
1993年「BS流行歌最前線」
まとめ
3rd アルバム『Versus』の1曲目を飾る本楽曲ですが、1st、2ndのイメージを覆す作風に、当時のファンは誰もが驚いたのではないでしょうか。
これ以前はラブソングの多かった彼らに、どのような心境の変化があったのか?
桜井さんは当時、アルバム『Versus』についてこのようにコメントしています。
「詞に関しても、あっと驚いちゃうような曲にしても、それは全部前から僕の中にも3人の中にもあるものだし、すごく好きなものだから…『Another Mind』とかね、そういう好きなものを3枚目だからやれるようになった5」
また、「『Another Mind』や『蜃気楼』は今回新しく出てきたものというよりも、僕らが前から好きだったものだったりする6」と語っていました。
こういったダークサイドの曲も、彼らの中に元々あったものだと。
また、中川さんも「この曲、確か前のツアー…札幌だったかな。リハやってるときにね、桜井がステージの後ろの方でギター弾いてて、それをテレコに録ってたんですよ。それ聴いて、“あっ、これカッコイイ…”って思ったんですよね。すごい自然に桜井の中から出てきてるものっていうか、そういう受け入れ方をした。それに、こういうタイプの曲が出てくるのはべつにおかしくないなと思ってたし。僕らの中では『Everything』作って『Kind of Love』作って、で、また今度『Versus』って、上手い具合につながってるなっていうのあるしね。だから“転換期”ってわけでもないし。延長線だな、と思う。7」
「もしかしたら、“今までと違う”みたいに言われるかなぁとか思ったりもしたけど、でもけっきょく『Another Mind』にしても、それを今までMr.Childrenで出してなかったけど、こういう一面も桜井の中にあるっていうのもわかってたし。8」
デビューからの2作では、王道のラブソングやポップなサウンドを前面に出してきましたが、それはある意味で「外向き」のMr.Childrenだったのかもしれません。
だから3枚目となる『Versus』では、そのベールを一枚はがし、4人が好きだった、より「内向き」で、人間の葛藤・矛盾といった側面を描く楽曲を、そろそろ届けてもいいんじゃないかと感じていたのでしょう。
最初はとてもかっこいい曲だなぁという印象で、聴くたびにこの曲の奥に潜むテーマに気づかされ、どんどんハマっていきました。
今では『Versus』の中で1、2を争うくらい好きな曲です。
「豆知識」の項目で、この曲は“アルバム最後の曲『my life』とリンクしている”という情報をお伝えしました。
当時の雑誌で田原さんがこのようなことを語っています。
「『my Iife』と『Another Mind』がリンクしてるらしいんですよ、詞とかが。“マイナスのもの”でも“喜劇”としてとらえていくみたいな、それが自分の人生なんだ、みたいなことを歌ってて。でもそういう中にも葛藤もあり、みたいな。9」
このコメントを読んで、なるほど、確かにこの2曲は表裏一体なのかもしれない…と感じました。
また、桜井さんはアルバム『Versus』について、「アルバムの詞を書いているときに、“大いなる矛盾”それをタイトルにしたら面白いかなとか思ってたんです。歌の中の主人公の内面に存在する、矛盾する自分みたいなものとか、でもその両方とも自分だっていうふうに認めつつ何かひとつの確信に向かっていく、みたいなものをわりと多く書いてたんですね。で、それはもちろん僕の中にもあるし、みんなの中にもあると思うんだけど、その“矛盾する気持ち”というのは面白いなと思ってて。それにいろんな視点、角度から当ててみていくとその奥行きの広さが出てくるしね。10」
「『my life』をアルバムの最後にしたいなっていうのはあったんです。だから同じ矛盾でも『Another Mind』みたいに終わっちゃうんじゃなくて、もちろんそういう要素もアルバムの中にはあるんだけど、最後はその矛盾した要素を喜劇にして終わりたいっていうのがあった。11」
『Another Mind』では、葛藤の渦中にいるリアルな苦しさが前面に出ていて、感情のうねりそのものが音楽になっている印象です。
一方で『my life』の主人公は、寂しさという感情のうねりを抱えながらも、それを受け入れ、“これが自分の人生なんだ”と微笑みをみせるように達観している。
だからこの2曲は対になるような存在で、アルバム『Versus』の中でそれぞれが担っている役割も納得です。
この歌は、自分の中にある“演じる自分”と“本音の自分”の分裂を描きながら、矛盾だらけの人間の姿をリアルに映しています。
最後まで答えは提示されません。
でも、そこにこそこの曲の強さがあり、聴く人それぞれの“Another Mind”と向き合わせる鏡のような作品になっているのだと思いました。
準備中
- 映画『Split the Difference』パンフレット ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- GB 1993年9月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎
- PATi-PATi ROCK’N’ROLL 1993年10月号 ↩︎