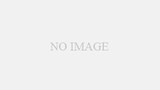Mr.Children「幸せのカテゴリー」の解説と歌詞考察だよ♪
本当の幸せはカテゴリーの外にある
楽曲紹介
楽曲収録CD
| 概要 | 収録作品 | 発売日 |
|---|---|---|
| 6th ALBUM | BOLERO | 1997年3月5日 |
作詞:桜井和寿/作曲:桜井和寿/編曲:小林武史&Mr.Children
アルバム『BOLERO』累計売上:328.3万枚
豆知識
アルバムジャケット情報
ジャケットは異国の少女が1人、一面に咲き広がる向日葵の中でボレロの代名詞でもあるスネアを叩いている写真で、メンバー以外の人物がジャケットに起用されたのは本作が初。
- ブルガリアのひまわり畑をイメージ
- ウクライナで撮影された
- 女の子は映画「ブリキの太鼓」で子供が狂ったように小太鼓を叩くシーンがあり、そのイメージで作られた
- メンバーは女の子に会ったことはないが、女の子の母親には会ったことがある
- アートディレクター:信藤三雄
MV(ミュージックビデオ)情報
・なし
ミュージックビデオはございません
タイトルについて

例えば『音楽』というカテゴリーが「ロック」「ポップ」「クラシック」などのジャンルに枝分かれしていくように、『幸せ』というカテゴリーも様々な要素で形成されていきます。
どう行動すれば『幸せ』になれるのか?
『幸せ』になるためには決まった条件などがあるのでしょうか?
“幸せのカテゴリー”とは、二人が無意識に信じ込んでしまった“理想の形”です。
歌詞考察
1番 Aメロ(通り過ぎる〜)
通り過ぎる愛の言葉
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
唇を重ねたって 孤独な風
胸を吹き抜ける
「好き」とか「愛してる」とか言葉にしても、もう互いに心に届くことはなく、ただ右から左へ通り過ぎていくような状況。
キスをしてもそこに愛はなく、孤独を感じさせる冷たい風が胸を吹き抜ける。
そんな冷め切った二人の関係が描かれています。
1番 Aメロ2(出会った日の〜)
出会った日の弾む鼓動は
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
日常と言う名の フリーザーの中で
とうに凍りついてる
男女の関係性が徐々に冷めていく様子が“日常”=フリーザー(冷凍庫)と比喩することで、より強調されています。
恋の始まりは胸が高鳴り、ときめきや情熱、そして純粋な温かい気持ちでいっぱいです。
でも日々の繰り返しや慣れが、かつての熱い気持ちやときめきをじわじわと凍らせてしまった。
当時の感情はずっと前から新鮮さを失っていて、徐々に冷たく硬く、動かぬものになってしまったのです。
1番 Bメロ(夢のような〜)
“夢のような毎日が 手を伸ばせばそこに立ってる”
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
そんなふうに自分に言い聞かせて過ごしてたけど
主人公は“夢のような毎日”という思い描いていた幸せが、“すぐ手の届く場所にある”、あるいは「今すでに手に入れているんだ」と、自分に信じ込ませようとしていました。
しかし実際は、本心では気づいていた違和感や物足りなさを押し込めていただけ。
「幸せであるはずだ」と信じ込みたい自分と、「実はもうそんな毎日じゃない」と気づいている自分の心のギャップが描かれています。
1番 サビ(傷つく事〜)
傷つく事 傷つける事が
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
互いになんとなく面倒くさかっただけ
形式だけに 目を奪われて
ただスマートに納まってようとした二人
今となっては
消えゆく幸せの Category
感情のぶつかり合いを避けながら暮らす二人。
それを「なんとなく面倒くさかっただけ」と言ってしまうのは、よくあるリアルな倦怠です。
“形式”とは、幸せになるための条件。
例えば「結婚」「安定した生活」「世間的に“順調”と言える姿」です。
つまりこの“形式”は、外から与えられた幸せの定義。
その形を守るため、ただスマートに、波風立てずに、利口に、時には適当にうまくやっていた。
「“一緒にいること”や“恋人でいること”が幸せの形であるはずだ。」
「それに当てはまっているから、自分たちは幸せなはずだ」と信じたかった。
でも実際には、その条件を満たしても心は満たされていない。
「幸せのカテゴリー」とは、二人が無意識に信じ込んでしまった“理想の形”。
本来の「幸せ」は、形式ではなく中身で決まるもの。
それに気づいたときには、もう手遅れ。
二人が信じていた“幸せ”というカテゴリーは崩れていくのです。
2番 Aメロ(誰かの忠告も 〜)
誰かの忠告も聞かず
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
不吉な占いを 笑い飛ばしてた
まだ無防備だった頃
付き合いたての頃は、不安もなく怖いもの知らずだっため、周りからの心配や忠告を気にも留めなかった。
不吉な占いも笑い飛ばしていた。
まだ疑うことを知らない無防備な二人は、自分たちの信じたい“幸せ”にしがみついていたのです。
2番 Bメロ(限りなく〜)
限りなく全てが 上手くいってるように思ってた
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
幸せってあまりにもろく儚いものなんだね
「形式だけに 目を奪われて」というフレーズがあったように、過去の錯覚に気づいた主人公。
実際には二人の間に小さな綻びがあったのだろうけど、見えていたのは表面だけ。
あの頃の自分たちはまだ何も分かっていなかったと、身をもって知ることとなりました。
二人はこれまで幸せだったと思っていた。
でも、それは“そう見えていただけ”で、本当はとても壊れやすくて、繊細で不確かなものだった。
そして気づかぬうちにその幸せは、崩れてしまったのです。
2番 サビ(日のあたる〜)
日のあたる場所に続く道
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
違う誰かと歩き出せばいいさ
恋人同士ではなくなったら
君のいいとこばかり思い出すのかな?
当分はそうだろう
でも君といるのは懲り懲り
「日のあたる場所」とは“それぞれが願う幸せ”。
君を手放すことを決めた主人公は、「違う誰かと歩き出せばいいさ」と、突き放すような、達観したような気持ちで、「もう互いの未来は別々の場所にある」と受け入れている。
ただ、恋愛中は相手の欠点や喧嘩ばかりが気になるのに、終わってからは、なぜか良かった思い出ばかりが蘇ってくるものです。
主人公もそれは分かっている。
でも「もう同じ失敗は繰り返したくない」という気持ちから、「君といるのは懲り懲り」と、本音をバサッと言い放ちました。
これまで積み重ねてきたものに蓋をして、別の未来を見ようとしています。
Bメロ3(本当の自分〜)
本当の自分なんて 何処にもいないような気がしてる
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
だからこそ僕らは その身代わりを探すんだね
恋の旅路は続くんだね
「ありのままの自分でいたい」と思っても、相手に好かれたいがために「演じてしまう」ことがあります。
その結果、「じゃあ、本当の自分ってどこにいるの?」という不安が残る。
「身代わり」=“本当の自分”の代用品。
本当の自分の居場所が分からないから、誰かと一緒にいることで「自分はここにいていい」と感じたいという欲求です。
僕らはこれからも、“誰か”を通して“自分”を見つけようとする。
でもその旅には、終着点なんてないのかもしれない。
ラスサビ(もう何も〜)
もう何も 望みはしないけど
<出典>Mr.Children/幸せのカテゴリー 作詞:桜井和寿
最近はちょっぴり解りかけてるんだ
愛し方って もっと自由なもんだよ
君もいつしかその事に気付くのだろう
じゃあ その日まで
さよなら幸せの Category
別れを決めた今、「何も望まない」という諦めから、欲しがらないことで大切なことに気づいた主人公。
“愛し方って もっと自由なもんだよ”
「〜しなきゃ愛じゃない」「こういう関係じゃなきゃ幸せじゃない」そんな枠から少し抜け出して、自分なりの答えを見つけ出せばいい。
離れ離れになることで、僕だけじゃなく君もきっとそのことに気付くのだろう。
「幸せとはこういうもの」という枠組みに縛られた恋に別れを告げて、それぞれが自分なりの愛、自分なりの幸せを探す旅に出るのです。
誰かにとっての幸せも、自分にとっての幸せも、同じ“カテゴリー”に収まるとは限らない。
本当の幸せは、カテゴリーの外にある。
「不完全でも、自由で正解のない自分だけの幸せを見つけていいんだ」という、哲学的な歌詞でした。
聴きどころ
メロディー
田原さんは当時この曲のメロディーを「童謡っぽい」と語っていました。
「僕はこの曲、前に桜井に聴かせてもらってて、しばらく忘れてたんですけど、家でふと煙草吸ってる時、思い出したんです。メロディを。あれ、この曲って童謡だったっけって。そしたらこの曲だった。3」
別の雑誌でも「換気扇の前で煙草吸って、このメロディ思い出してね。なんか、“赤とんぼ”とか…あのへんの童謡っぽいなって思った。4」
つまり童謡のようにほのぼのとした“ふと口ずさんでしまうメロディー”ということでしょう。
Aメロは若干歌い回しが難しいですが、それ以降はとても心地良い旋律ですね。
アレンジ
歪んだエレキギターのオブリやアルペジオが心地良く、間奏では鉄琴の一種であるビブラフォンという楽器の温かいソロが印象的。
トラックの終わりには『everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-』へ繋がるように、ちょこっとドラムを差し込んであるのも面白いですね。
レコーディングの際、ミックスにはとても悩んだそうです。
桜井さんは「歌詞の寒々とした感じを聴かせるベクトルか、ただの物語で聴かせるベクトルなのか、それで悩んだ。でも、出だしとか、一瞬、あの『星になれたら』の頃のMr.Childrenが帰ってきたと思いきや…違うんですよね。5」と語っていました。
初期のようなポップな曲調だけど、『BOLERO』の中でも決して浮かない大人なサウンドになっています。
著名人の感想
随時更新します。
ライブ披露
ライブ
- REGRESS OR PROGRESS
- THE SECRET LIVE
オススメ映像作品
現在映像収録作品はございません。
テレビ
- なし
まとめ
アルバム『BOLERO』の中でシングル曲を除けば、最もキャッチーで聴きやすい曲です。
ベースの中川さんは当時のインタビューで「この曲って、曲調的には、かつての僕らの雰囲気もある。だからふと、『Kind of Love』の頃のポップさもイメージしてみたけど、できあがってみりゃ、全然あの頃のようにはいかなかったという。あの活きのいい感じはならなかった。6」と語っていました。
確かに口ずさみたくなる曲調やメロディーは、爽やかな“あの頃”のMr.Childrenを彷彿とさせます。
でもそれに反して歌詞は、突き放すような言葉や皮肉を込めたようなフレーズが散りばめられていて、正直聞くに堪えないものになっています。
言うなれば“恋人の前では絶対に歌ってはいけない曲”。
でも僕はこの曲大好きです。
このサイトではMr.Childrenにとってマイナスとなり得ることを一切発信しないよう心がけているので、事実だけさらっと読んでいただけたらと思いますが…、アルバム『BOLERO』がリリースされるひと月前の1997年2月、女性週刊誌で桜井さんの不倫が報じられました。
それもあり、この曲は桜井さんのプライベートな感情を歌にしたものだという解釈もよく見られます。
この曲がロンドンでレコーディングされたのは1996年6月。
確かにこういった気持ちになっていた時期なのかもしれません。
でも『幸せのカテゴリー』という楽曲を通して描かれているのは、恋愛の終わりをきっかけに、「幸せとは何か」「愛するとはどういうことか」を見つめ直していく“心の旅”のような気もしています。
「愛し方って もっと自由なもんだよ」
この曲の特に印象的なフレーズですが、人は痛みを経て本質的な気づきにようやく辿り着けることがあります
主人公が気づいた「自由な愛」。
「君もいつしかその事に気付くのだろう」
別れを悲劇としてではなく、成長の過程として描き、聴く人それぞれに、自分なりの幸せのかたちを問い直すきっかけを与えてくれるように感じました。
ただやっぱり、恋人の前で歌うとぶん殴られそうな曲であることには違いないですね。
- B-PASS 1997年4月号 ↩︎
- WHAT’s IN? ES 1997年4月号 ↩︎
- 月刊カドカワ 1997年4月号 ↩︎
- WHAT’s IN? ES 1997年4月号 ↩︎
- WHAT’s IN? 1997年3月号 ↩︎
- 月刊カドカワ 1997年4月号 ↩︎