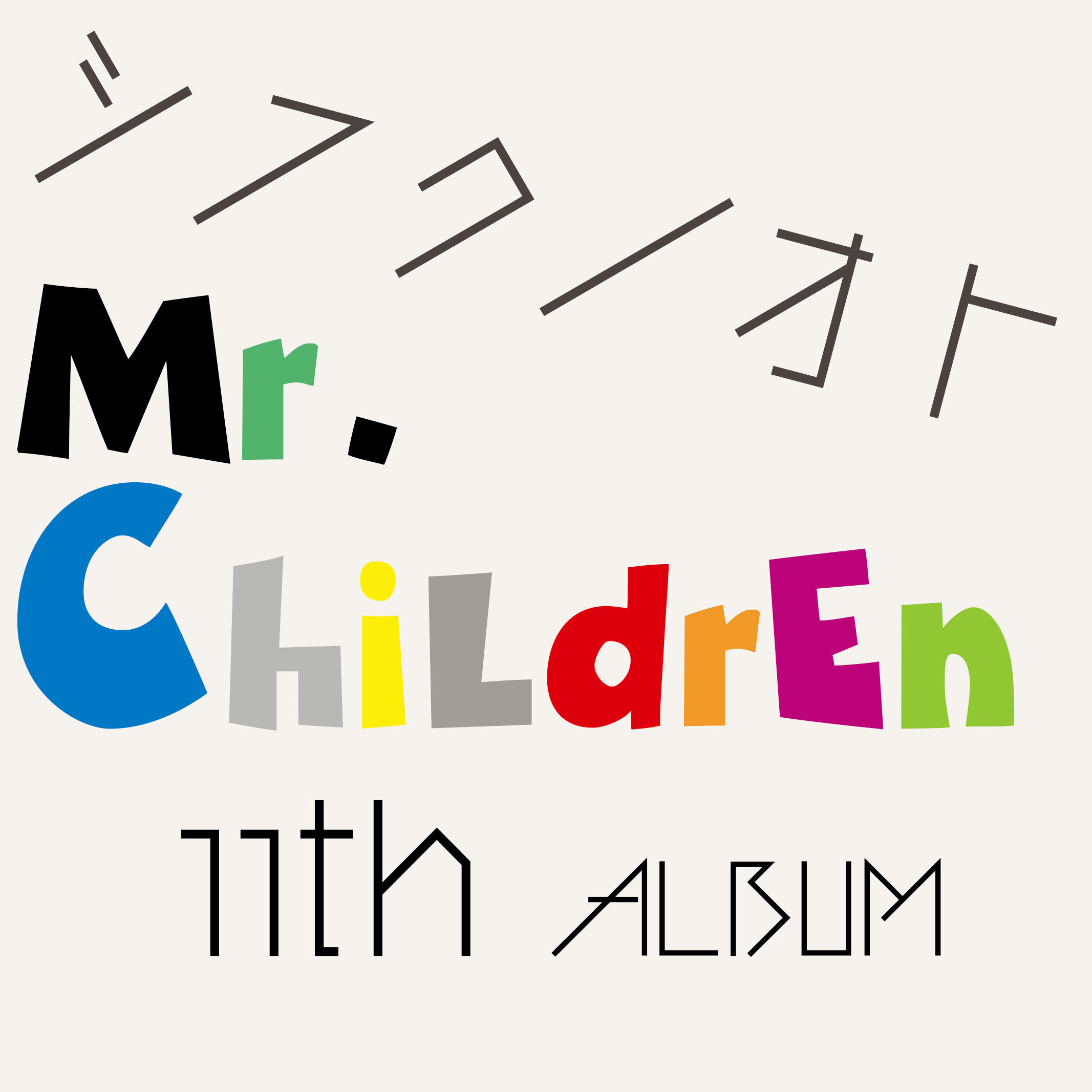Mr.Children「ランニングハイ」の解説と歌詞考察だよ♪
ありのままの自分を隠さずに進んでいこう
楽曲紹介
楽曲収録CD
| 概要 | 収録作品 | 発売日 |
|---|---|---|
| 27th Single | 四次元 Four Dimensions | 2005年6月29日 |
| 12th ALBUM | I ♥ U | 2005年9月21日 |
| BEST ALBUM | Mr.Children 2001-2005 <micro> | 2012年5月10日 |
| 36th Single | ヒカリノアトリエ | 2017年1月11日 |
作詞:桜井和寿/作曲:桜井和寿/編曲:小林武史&Mr.Children
シングル『四次元 Four Dimensions』累計売上:92.6万枚
アルバム『I ♥ U』累計売上:113.7万枚
※『ヒカリノアトリエ』にはライブVer.「虹 Tour 2016.11.7 FUKUI」を収録
豆知識

映画『フライ,ダディ,フライ』主題歌だよ!

映画主題歌は1995年に公開された『【es】 Mr.Children in FILM』以来10年ぶりだな。

提供するのはこの曲が初めてよ!

『フライ,ダディ,フライ オリジナル・サウンドトラック』には『ランニングハイ Piano Version』が収録されているよ♪
アルバムジャケット情報
- ジャケットを手掛けたのはイギリスのデザイン会社「TOMATO」
- シングルタイトル『四次元』は「よじげん」ではなく「よんじげん」(次元の種類ではなく数を表している)
MV(ミュージックビデオ)情報
なし
ミュージックビデオはございません
タイトルについて

仮タイトルは『歪み(ひずみ)』だった。
桜井さんは仮タイトルだった『歪み』をとても気に入っており、タイトルが変わったときにとてもガッカリしたそうです。桜井「この曲で描かれていること、それ自体が『歪み』なんだなぁって思ってましたから。」1
『ランニングハイ』とは、走っているときの高揚感を意味しています。
それは苦しさを超えた先にある感覚。
歌詞考察
1番 Aメロ(甲「理論武装で〜)
甲「理論武装で攻め勝ったと思うな バカタレ!」
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
乙「分かってる 仕方ないだろう他に打つ手立て無くて」
甲「威勢がいいわりにちっとも前に進めてないぜっ」
乙「黙ってろ!この荷物の重さ知らないくせして」
冒頭は二人の登場人物が対話をしている形式で始まります。
甲が相手で、乙が主人公。
甲「理論武装で攻め勝ったと思うな バカタレ!」
甲は、言い訳や表面的な論理で自分を守ろうとしている乙に対して、「攻め勝ったと思うな」という言葉で、「それで自己満足している場合じゃないぞ」と指摘しています。
それに対して乙が反論。
乙「分かってる 仕方ないだろう他に打つ手立て無くて」
乙は、自分はこの限られた状況の中でも、打つ手が無くなるくらい必死であることを訴えています。
甲はさらに乙の行動を揶揄していきます。
甲「威勢がいいわりにちっとも前に進めてないぜっ」
見かけは威勢よく振る舞っているが、乙は実際に何の成果も出せていないと、さらに指摘。
乙はまたも反論。
乙「黙ってろ!この荷物の重さ 知らないくせして」
「荷物の重さ」とは、乙(主人公)が抱えているプレッシャーや責任、悩みの比喩。
自分を責め立てる甲に対し、「お前にはわからない!」と感情が爆発しています。
ここまでは単純な二人の人物の対話に見えますが、実は次のフレーズへ進むと「甲」と「乙」は主人公の心の中の「自分」と「もう一人の自分」という構造になっているのが分かります。
1番 Bメロ(向こう側にいる〜)
向こう側にいる内面とドッヂボール
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
威嚇して逃げ回り受け止めて弾き返す
「向こう側にいる内面」とは、主人公自身のもう一人の姿、つまり「甲」を指していると考えられます。
その内面とのやり取りはただの会話ではなく、“ドッヂボール”のように、ぶつけたり、避けたり、受け止めたりという激しい“駆け引き”。
主人公は今、そんな葛藤状態であることが分かります。
1番 サビ(「もう疲れた〜)
「もう疲れた誰か助けてよ!」
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
そんな合図出したって
誰も観ていない ましてタイムを告げる笛は鳴らねぇ
なら 息絶えるまで駆けてみよう 恥をまき散らして
胸に纏う玉虫色の衣装をはためかせていこう
主人公の心は折れかけています。
でもどんなに助けを求めても周りの人々は気づいてくれない、あるいは関心すら持ってくれない。
立ち止まるチャンスすらも与えられない過酷な状況です。
しかし主人公は、そんな諦めや孤独感を受け入れたうえで、だったら「息絶えるまで駆けてみよう」、「力尽きるまで前に進もう」と自分自身を奮い立たせます。
周りの目や評価を気にせず、カッコ悪くても泥臭くても構わない。
大切なのは純粋に自分が「どう生きたいか」です。
「玉虫色」は光の具合で様々な色に見える特性があります。

これにより、「解釈の仕方によってどのようにも受け取れる曖昧で都合のいい表現」の比喩として使われます。
この曲の「胸に纏う玉虫色の衣装をはためかせていこう」とは、弱さと強さを纏ったこのありのままの自分を隠さずに進んでいこうという覚悟が込められています。
2番 Aメロ(苛々して仕方ない〜)
苛々して仕方ない日は
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
疲れた体を
都合のいい恋にあずけて
終われば 寝た振りして
あれっ 俺ッ 何してんだろう?
忘れた 分からねぇ
太陽が照りつけるとやけに後ろめたくて
ストレスや不満が溜まった主人公は、その苛立ちから逃避するために一時的な快楽を求めます。
それが終わると我に帰り寝た振りをする。
もうその行為をした理由や目的さえも分からず、朝になるとその虚無感から、後めたい気持ちになってしまった。
苛立ち、現実逃避、虚無感、後ろめたさという人が抱える負の感情のサイクルが描かれています。
2番 Bメロ(前倣え〜)
前倣え 右へ倣えの欲望
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
気付けば要らんもんばかりまだ間に合うかなクーリングオフ
僕らは個人の自由や選択が制限された集団の中にいて、無意識に世間に流されながら生きていこうとする。
集団的な同調によって生まれる欲望は、必ずしも本質的な欲求ではありません。
社会が押し付ける価値観やトレンドに流されて、本当に必要でないものを欲しがってしまう。
気付けば要らんもんばかり。
自分が“選んでしまった”過去を取り消したい。
「まだ間に合うかな」
その一言に、後悔と思いを新たにする気持ちが込められていますね。
2番 サビ(亡霊が出る〜)
亡霊が出るというお屋敷を
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
キャタピラが踏みつぶして
来春ごろにマンションに変わると代理人が告げる
また僕を育ててくれた景色が 呆気なく金になった
少しだけ感傷に浸った後「まぁそれもそうだなぁ」
「あのお屋敷には“亡霊”が出る」
僕が小さい頃から空き家だったその家は、そんな噂が立つくらいそこにずっとあった。
それを今、キャタピラが無機質に呆気なく踏みつぶしている。
その空き家は来春ごろにマンションに変わるらしい。
主人公が昔から見ていた景色や思い出があっという間にただの「金」という紙切れに変わってしまいました。
主人公は一瞬、過去への感傷や喪失感に囚われますが、その感情に長く留まることなく現実に引き戻されます。
過去に縋らず現実を受け入れて前に進む。
そう思える強さを身につけた主人公を描いているようなフレーズです。
3番 Bメロ(時代とか〜)
時代とか 社会とか
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
無理にでも敵に仕立てないと
味方を探せない愉快に暮らせないよ
この時代や社会を生きるうえで、上手く立ち回るには自分の力だけでは到底何もできません。
味方が必要になる。
しかし「味方」という概念を成立させるには共に立ち向かう「敵」を設定する必要があります。
何らかのターゲットを見つけ、そこに攻撃すれば面白がって味方がつく。
味方がいれば安心する。
これは世間からの孤独を恐れつながりを求めるがあまり、何が正しいのか分からなくなっている現代人への皮肉です。
ラスサビ(いつかこの〜)
仕組んだのは他の誰でもない
<出典>Mr.Children/ランニングハイ 作詞:桜井和寿
俺だって 自首したって
誰も聞いてない まして罪が軽くなんかならねぇ
なら 息絶えるまで駆けてみよう 恥をまき散らして
退きどきだと言うなかれ素人! まだ走れるんだ
息絶えるまで駆けてみよう 恥をまき散らして
胸に纏う玉虫色の衣装を見せびらかしていこう
これまでの失敗や挫折、その過ちや後悔は、他人のせいではなくあくまで自己責任であると受け入れる主人公。
ただ、それが分かったところで周りはそれを気にしないし、取り返しもつかない。
ならいっそ世間からの評価を恐れずに、自分らしく恥をまき散らしながら全力で堂々と走り続けようと心に決めました。
「退きどきだ」と自分の限界を決めつける声に従う必要はなく、自分の可能性を最後まで信じて、ありのままの自分で。
弱さをさらけ出しながら、それをエネルギーに変えて走り続ける主人公の姿は、きっと誰よりもカッコよく、誰よりも爽やかな汗を流していることでしょう。
どれだけ足掻いても世間は変わらない、でも自分は変えられる。
そんな強いメッセージを感じました。
聴きどころ
メロディー
まさに大きく腕を振りながら駆け抜けるような勢いのあるメロディーです。
歌入れの時桜井さんは体調があまり良くない状態だったそうで、本人曰く「この曲を作るためには必要な体調の悪さだった2」と語っています。
そんな体調の悪さなどものともしないハイトーンの連続が、弱さをさらけ出しつつもエネルギーに変えて走り続ける主人公の姿と重なります。
桜井さんの全力疾走にはいつも感情を揺さぶられますね。
個人的に最も好きなポイントはラスサビの「恥をまき散らして」の「ら」のロングトーン。
超高音のファルセットで歌われており、その声に毎度心を鷲掴みにされます。
アレンジ
ブラスメインのアレンジ。
とにかく勢いが凄い、それに尽きると個人的には思います。
アルバム『I ♥ U』に収録されている楽曲は、そのほとんどがデモテープ無しのセッションで作られており、この『ランニングハイ』もその一つです。
はじめに田原さんが「ジャッジャッジャッ」とギターを刻み、そこにナカケーのベースが乗っかり、桜井さんが歌い出したらJENのドラムが合わせていく。
そういった衝動に委ねた方法で制作されました。
しかもアルバム制作でいちばん初めにセッションをした曲。
だからこその、楽器同士の駆け引きや張り合いが、スピーカーから目に見えるように感じられます。
この曲のテーマにぴったりなアレンジに仕上がっているなぁと思いました。
小林さんは、ホーンの感じとか、スタジオでアレンジをしていた時、「60年代後半のマイルス・デイヴィスみたい」と言っていたそうです。3
著名人の感想
※情報があり次第記載
ライブ&テレビ披露
ライブ
- ap bank fes ’05
- SETSTOCK’05
- HIGHER GROUND 2005
- ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2005
- SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2005
- DOME TOUR 2005 “I ♡ U”
- “HOME” TOUR 2007
- 京都音楽博覧会2016
- Hall Tour 2016 虹
- DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25
- Traveling Ska JAMboree 2022-2023
オススメ映像作品
MR.CHILDREN DOME TOUR 2005“ I ♥ U ” ~ FINAL IN TOKYO DOME ~
どの映像作品も甲乙つけ難いですが、『”HOME” TOUR 2007』では歌詞の「時代とか 社会とか 無理にでも」を「時代とか 社会とか でっちあげてでも」に変更されていて、そのワンフレーズが超絶カッコいいのも大きなポイントです。
テレビ
2005年07月01日「僕らの音楽」
2005年07月09日「COUNT DOWN TV」
まとめ
自身の映画を除き、初の映画主題歌となった曲ですが、そのきっかけは2001年に発売された21st Single『youthful days』まで遡ります。
桜井さんは過去に、映画『フライ,ダディ,フライ』の脚本・原作を務める小説家、金城一紀さんの小説『GO』に強い影響を受けて作った曲がありました。
それが『youthful days』です。
2001年、『youthful days』の歌詞を書いた後、偶然にも同時期に『GO』映画版の主演、窪塚洋介さんとの雑誌対談がありました。
そこで原作に影響を受けた曲(『youthful days』)があることを語ります。
これを知った金城さんは、2003年発売の小説『フライ,ダディ,フライ』の冒頭で、Mr.Childrenの楽曲『光の射す方へ』の歌詞を抜粋し、ミスチルにラブコールを送ります。
お互い尊敬しあう関係が続く中、2004年10月ごろ、「同映画主題歌にミスチルを」という案が製作サイドから飛び出し、編集ビデオを桜井さんとプロデューサーの小林武史さんに送付。
2つ返事で快諾したといいます。
こうして『ランニングハイ』が生まれました。
曲について桜井さんは「この映画の魂を汚さぬよう大切に受け継いで、息を切らして叫び、僕らなりに全力疾走してみました」とコメント4。
金城さんも、大のミスチルファンで知られる主演の岡田准一さんも大喜びしたとのことでした。
初めてこの曲を聴いた時は、演奏と歌に良い意味での乱雑さがあり、すごくハジけた曲だなぁと感じました。
まるでリアルなセッションプレイをそのまま録音したような生感もあり、聴いていると気分が高揚していきます。
歌詞については、「恥をまき散らしでも必死になって生きろ」というメッセージがグッと突き刺さる曲でした。
しかしその中でも現代への皮肉が込められたフレーズもあります。
まず「前倣え 右へ倣えの欲望 気付けば要らんもんばかりまだ間に合うかなクーリングオフ」というフレーズ。
現代の多くの人が、SNSやメディアによって本当に必要なものではない流行やステータスを追いかけがちです。
他人と同じであることに安心感を覚え、自分で考えることを放棄。
そしてその過程で「自分らしさ」を見失う。
さらに「時代とか 社会とか 無理にでも敵に仕立てないと 味方を探せない 愉快に暮らせないよ」というフレーズも
おそらくネット社会に対する皮肉ですが、「何故わざわざ敵を作るのか?」「敵を作らずに味方を見つけることは不可能なのか?」そんな問題提起のようにも感じます。
この曲は2005年にリリースされた曲ですが、時代が進むにつれ、それらの問題はどんどん深刻化しています。
恥を晒せばすぐに誰かに叩かれる。
今もなお、これらのフレーズが響いてしまう現実。
こういった歌詞に共感しなくてもいい時代は来るのでしょうか?
昨今のSNSを傍観しながらも、そんなことを思う今日この頃です。
とはいえ、背中を押してくれる歌詞であることは間違いありません。
『フライ,ダディ,フライ』はどこにでもいるような“おっさん”が学生ボクサーに立ち向かうお話です。
「息絶えるまで駆けてみよう 恥をまき散らして」
魂を汚さぬよう僕も僕なりに、たまには全力疾走してみたいと思います。